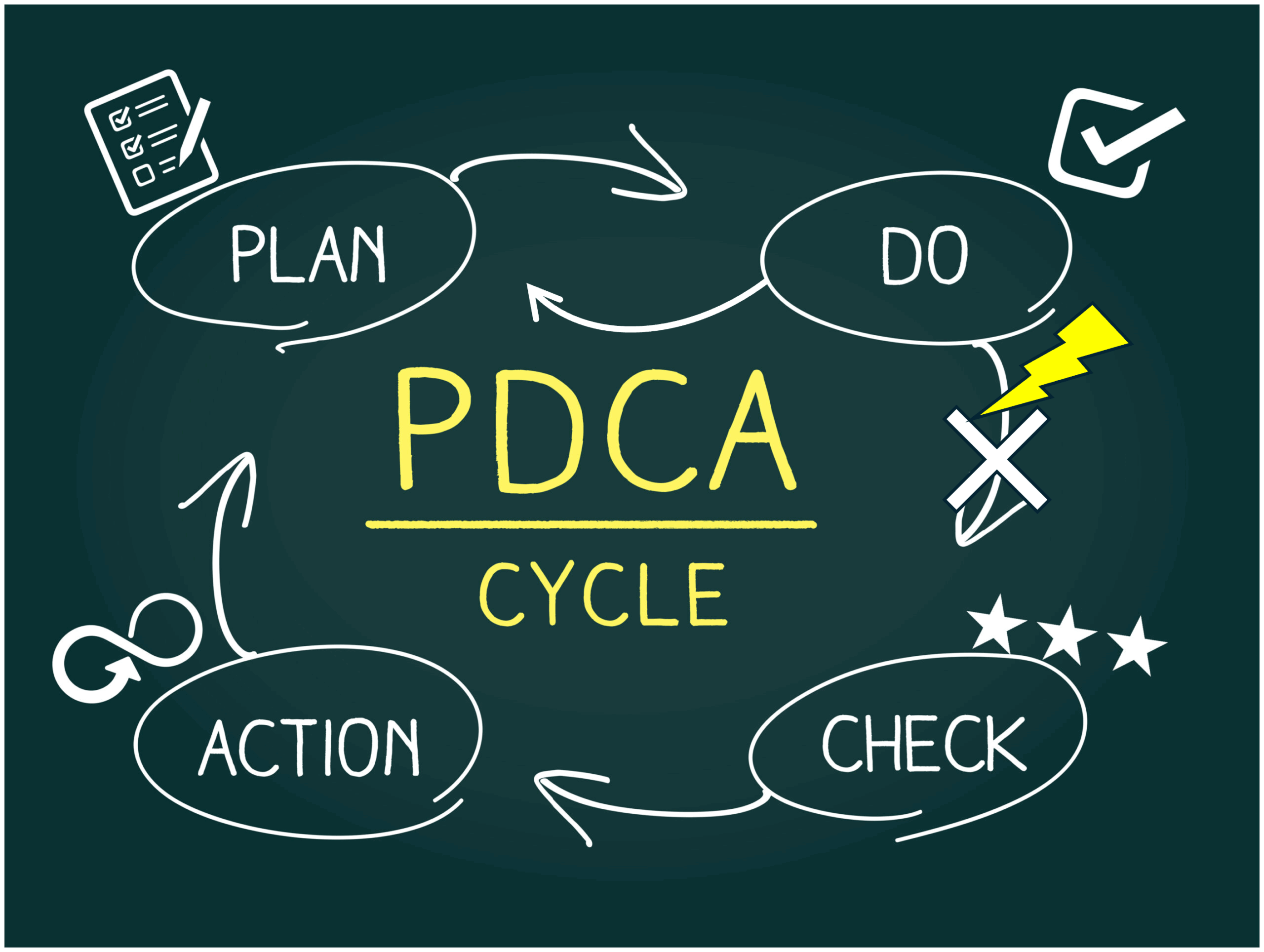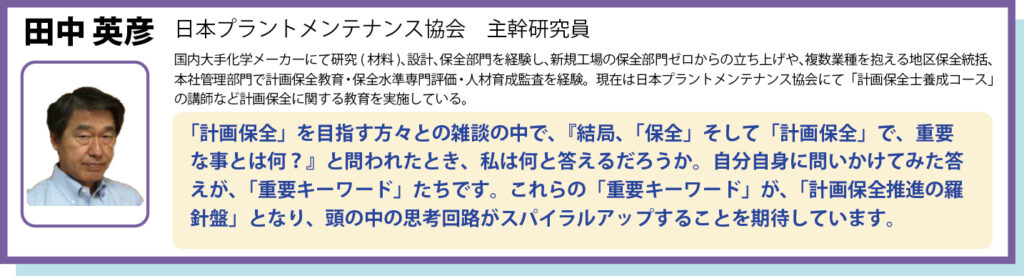
羅針盤その6 「数値で“見える化”」
「数値で示そう」「グラフ化しよう」と、我々は教えられてきた。正しいアドバイスだと考える。数値の魔術師になってはならないが、数値第一の共感者になるのは大歓迎だ。
保全目標を数値で定める。機器の管理基準や協力企業への指示も数値で示し、その数値の根拠を示す。傾向管理は数値化しグラフ化する。経年劣化の程度を数値で示す。故障件数など保全の結果を数値で示す。保全予算と実績を数値で示す。保全水準のレベルを数値で評価する。いずれも大切だ。
数値は誰が見ても等しい感覚で捉えることが出来る。傾向をグラフ化し、その上昇下降をビジュアルに感じることも出来る。説明も容易となる。目標に設定した場合、組織のベクトルを合わせることにも繋がる。
数値化する場合、その正確さが求められることはもちろんのことだ。レポートを作成する際、文章の間違いには多少は目をつぶって許されるが、数値だけは小数点以下の有効数字までの正確さが求められる。数値はそのままの姿(=値)が覚えられ、印象に残るからだ。
種々の数値に意味があると前言したが、同時に、その数値の定義も同じように重要となる。確かな定義の下で収集されたデータでなければ、その数値そのものの意味は失せてしまうからだ。設備には多くの人数が関わる。その多くの人たちが、同じ土俵の下で、数値を眺めることが出来なければ、その数値は色あせてしまう。
そのため、「計画保全」では、用語の定義も重要視している。系列とは何か、停止時間をどのようにカウントするか、そもそも故障とは何か。
定義が明確で、且つ具体的な用例が示されていて、初めて複数のメンバーが同じスタンスでカウント出来ることになる。信頼ある数値が記され、その積み重ねは大きな意味を持つものとなる。定義を社内で一律にしておけば、異なる工場のデータを横並びに比較することも出来る。
「計画保全」に慣れない工場では、数値一つを定めるのに迷うことがある。意味を十分に理解し、数値を定めるにも訓練が必要になる。長けたメンバーが月報会などの討議の場に参加し、正しい数値が用いられているかをアドバイスすることも時には必要になる。
正しい数値を用いた「見える化」を強く意識し、あらゆる事柄の数値化を考えてみたいものだ。
●重要参考テキスト
・『MOSMS実践ガイド』(p115:機器別管理基準、p166:MQ、p174:月報、p176:用語、p185:予算、p262:指示検収票、日本プラントメンテナンス協会)
・「計画保全士養成コーステキスト」(p45:機器別管理基準、p64:予算、p76:MQ、p77:用語、p86:指示検収票、p105:月報、p119:保全水準、日本プラントメンテナンス協会)
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。